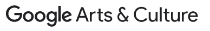中国やきもの史
中国のやきものは1万年以上の歴史を有しています。新石器時代の仰韶(ぎょうしょう)文化期には彩陶(さいとう)・紅陶(こうとう)・白陶(はくとう)がつくられ、龍山文化期には黒陶(こくとう)が盛んとなります。商〔殷〕王朝では、原始青磁とも呼ばれる灰釉陶(かいゆうとう)が登場します。春秋時代末から戦国時代には印文硬陶(いんもんこうとう)と灰釉陶が焼かれます。戦国時代には秦始皇帝陵の兵馬俑(よう)に代表される灰陶(かいとう)、加彩灰陶の俑が大量につくられました。後漢時代には副葬品を中心として鉛釉陶(えんゆうとう)が流行します。また、浙江省北部の越窯(えつよう)では本格的な青磁が登場し、三国時代から南朝にかけて青磁の生産が盛んとなり、その中には独特な造形の神亭壺(しんていこ)や天鶏壺(てんけいこ)なども見られます。一方、華北では北朝において鉛釉陶や青磁が生産され、とくに北斉時代には黄釉(おうゆう)に緑釉(りょくゆう)のかかる二彩や三彩(さんさい)などの鉛釉陶や白磁への萌芽なども見られるようになります。
唐時代には、文様や造形に国際的な文化の影響がみられ、加彩や三彩の器皿や俑が多くつくられます。華北では邢窯(けいよう)で隋時代から白磁がつくられ、定窯(ていよう)でも唐時代には白磁の生産が始まります。一方、青磁は越窯で生産が続き、晩唐から五代にかけての最高級品は「秘色(ひしょく)」と称され、青磁の代名詞にもなりました。また、長沙窯(ちょうさよう)では釉下彩(ゆうかさい)に銅や鉄を用いた水注や盤などがさかんにつくられ、海外にも輸出されました。
北宋時代には、牙白色の釉色や流麗な片切り彫りなどの文様を特色とする定窯の白磁が流行し、各地の窯に影響を与えました。耀州窯(ようしゅうよう)ではオリーブグリーンの釉色を特色とする青磁が焼かれ、河南省の汝窯(じょよう)では北宋末に宮廷用の優美な青磁が生産され、後の鈞窯(きんよう)にも影響を与えました。河南省、河北省、山西省などにはいわゆる磁州窯(じしゅうよう)系の窯が展開し、白化粧を活用した多彩な製品がつくられました。南宋時代には都のあった臨安(現在の杭州)に官窯(かんよう)が設置され、厚い釉薬や黒い胎土を特徴とした青磁がつくられ、また日本にも伝世品の多く知られる龍泉窯(りゅうせんよう)の青磁、建窯(けんよう)や吉州窯(きっしゅうよう)の様々な天目(てんもく)茶碗、景徳鎮窯(けいとくちんよう)の青白磁(せいはくじ)など各地で特徴あるやきものが生産されました。
元時代になると、景徳鎮では青花(せいか)の技術が完成し、酸化銅を顔料とした釉裏紅(ゆうりこう)も始まります。青花は中近東はじめ海外にも輸出されたほか、同時に龍泉窯青磁も大量に輸出されました。
明時代には、景徳鎮に御器廠(ぎょきしょう)が置かれ、宮廷用の陶磁器が焼かれました。洪武(こうぶ)帝代には海禁政策によりイスラム圏からのコバルト顔料の供給がとだえ、釉裏紅が多くつくられました。永楽(えいらく)年間〔1403~1424〕にはコバルト顔料の輸入が再開されます。宣徳(せんとく)年間〔1426~1435〕にはさまざまな技法が試みられ、活発な生産をくりひろげました。成化(せいか)年間〔1465~1487〕には完成度の高い小碗や小盤がつくられたほか、豆彩(とうさい)も登場しました。
嘉靖(かせい)年間〔1522~1566〕から、御器廠での生産を補うために生産レベルの上がった民窯(みんよう)に官窯製品の生産委託が行われました。さまざまな五彩(ごさい)がつくられ、厳格な官窯の作風が揺らいでいきます。万暦(ばんれき)年間〔1573~1620〕には五彩の種類は著しく増加していきます。いっぽう景徳鎮の民窯では金襴手(きんらんで)や芙蓉手(ふようで)などが焼かれました。官窯が衰退していく明末清初には民窯が活発になり、輸出先の好みに合わせた製品を生産しました。
清時代の康熙(こうき)年間〔1662~1722〕には御器廠が再開され、端整な宮廷用の陶磁器が生産されます。雍正(ようせい)年間〔1723~1735)と乾隆(けんりゅう)年間〔1736~1795〕には生産技法が頂点を極めました。