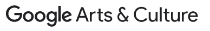日本やきもの史
日本陶磁の歴史は縄文土器に始まり、弥生土器、そして古墳時代〔3世紀~7世紀〕の土師器(はじき)や埴輪(はにわ)など土器文化が展開しました。5世紀には、朝鮮半島から伝わった新たな製陶技術によって高火度還元焔(かんげんえん)焼成の須恵器(すえき)が誕生し、原初的な釉薬の出現を見ました。飛鳥・奈良時代(538~794)には、中国や朝鮮半島の低火度鉛釉(えんゆう)陶器の影響を受け、色鮮やかな緑釉陶器や奈良三彩が登場し、さらに平安時代〔794~1185〕の9世紀になると愛知県の猿投窯(さなげよう)では人工的な釉薬を施した高火度焼成の灰釉(かいゆう)陶器の生産が始まりました。
平安時代の末から、堅く耐水性に優れた焼締(やきしめ)陶器が常滑(とこなめ)・渥美(あつみ)をはじめ越前(えちぜん)・信楽(しがらき)・丹波(たんば)・備前(びぜん)など各地で見られるようになり、中世を通じて実用器として大量に生産された。
鎌倉・室町時代〔1185~1568〕、中国渡来のいわゆる唐物(からもの)尊重の価値観を背景に、瀬戸・美濃(みの)地方では施釉陶器による中国陶磁写しの製品が盛んにつくられました。しかし、室町時代後期から「茶の湯」における独自の美意識が加わると、国産陶器、いわゆる「和物」の地位が飛躍的に向上しました。その結果、桃山時代〔1568~1615〕には、千利休〔1522~91〕の指導による長次郎の楽(らく)茶碗や、美濃(みの)の黄瀬戸(きぜと)・瀬戸黒(せとぐろ)・志野(しの)・織部(おりべ)の登場をはじめ、備前・信楽・伊賀(いが)・丹波・唐津(からつ)などでも茶陶を中心とした製品が数多く生み出され、日本陶磁史における一つの黄金時代を迎えました。さらに、江戸時代〔1615~1868〕の京都では、野々村仁清(にんせい)〔生没年不詳〕や尾形乾山(けんざん)〔1663~1743〕に代表される色絵(いろえ)陶器を中心とした優雅な京焼が一世を風靡(ふうび)しました。
一方、九州の有田(ありた)一帯〔肥前〕では、朝鮮半島の陶工の技術を基礎に、1610年代に日本で初めての磁器がつくられ、製品の積み出し港にちなみ「伊万里焼」の名で知られるようになりました。当初、中国景徳鎮の青花磁器を手本とした伊万里焼は、その後、中国から上絵付である色絵(いろえ)の技法も吸収するなど急速な発展を遂げ、17世紀後半から18世紀前半にかけて、オランダ東インド会社を通じて、ヨーロッパなどにも輸出されて一躍脚光を浴びました。初期伊万里、古九谷(こくたに)様式、柿右衛門(かきえもん)様式、金襴手(きんらんで)に代表される古伊万里様式など、伊万里焼は時代に応じて様々なスタイルを生み出し、日本各地に流通しました。さらに、佐賀・鍋島藩の御用窯(ごようがま)で徳川将軍家への献上を目的につくられた鍋島(なべしま)焼は、精緻なつくりと洗練された文様デザインを特徴とし、日本磁器の最高峰として知られています。